

測定用の治具を作ったら、測定のためにスピーカーを買い集める羽目になってしまった
真空管アンプでは、出力トランスの2次側巻き線とスピーカーのインピーダンスを合わせて整合性を取る必要があります。とはいうものの、たいていの出力トランスには2次側に 8Ω や 4Ω の端子がついている一方で、6Ωの端子を持った出力トランスは少なかったりします。また、スピーカーのインピーダンス公称値と実際のインピーダンスの値が違うということも実際にはままあるようです。(例えば、実際のインピーダンスが4Ωのスピーカーを出力トランスの 8Ω 端子に繋いたときの方が 4Ω 端子に繋いだときよりも出る音が大きくなるため、表向きのスピーカーのインピーダンス値を4Ωよりも大きくする戦略をメーカーがとるケースがあります)
以前から 6Ω スピーカーはアンプの 8Ω端子、4Ω端子どっちに繋いだらよいのだろう?という疑問は持っていました。ぺるけさんの見解によれば『6Ωスピーカーは4Ωにつなぐのが(歪みが少なくなるので)正解』とのことなのですが、それはあくまでもスピーカーのメーカーが上に書いたような嘘をついていないことが前提になりますので、実際のところはスピーカーのインピーダンスを実測してみないと本当の答えは分かりません。そこで、貸出目的で 6BM8 全段差動プッシュプルアンプを製作したのを機に、手持ちのスピーカーの測定を行ってみることにしました。
インピーダンスを測定に使用した回路は下図のようなごく簡単なもので、0.1Ω 抵抗にかかる電圧を Er、スピーカーにかかる電圧を Es とすると、スピーカーのインピーダンスは Es × 0.1 / Er で求まるという寸法です。0.1Ω 抵抗には誤差 5% の酸化金属皮膜抵抗を使用していますが、抵抗値の誤差には目をつぶることにします。

| 方式 | 1Way スピーカー・バスレフ型 |
| ユニット | 115mm コーン型フルレンジドライバー |
| インピーダンス | 6Ω |
| 防磁設計 | 〇 |
| 許容入力 | 60W |
| 入力感度 | 88dB (1W, 1m) |
| 周波数特性 | - |
| サイズ | 270(W) x 168(H) x 180(D) mm |
| 重量 | 4.2kg |
私にとってはじめての真空管アンプ(TU-870)を購入したのと同時期に入手したものです。当時はオーディオに関する知識も経験値もゼロに等しい状態だったのでスピーカーの選び方が皆目わからず、デスクトップ用に MM-1 を使っていたことや、家の中にあった通販カタログにたまたま WBS-1EX が載っていたことから、それに付属していたスピーカーである 121 に決めたような覚えがあります。
ただ、全段差動アンプを作るようになってから気づいたのですが BOSE 社の製品は独特の「味付け」といいますか、作為的な音作りをする傾向が強いようです。以前に BOSE の CD ラジオ試作機を聴く機会があったのですが(WaveRadio/CD よりも大きくてゴツいやつでした)、前述の MM-1 と同様にニアフィールドの空間に頑張って音場感を作り出そうとしているために、音源が本来持っている空気感が失われてしまっていました。
逆に言えば、BOSE 社は自社製品それぞれに対して相応のポリシーを持って製品や音質のチューニングを行っているということです。BOSE といえば 101MM が日本国内では有名ですが、これは設備や店舗向けに開発された商品で聞き取りやすさ・聞き疲れにくさ・耐久性といった点に重きがおかれており、音楽鑑賞を目的に設計されたものではありません(なので、ピュアオーディオ目的で 101MM を選ぶとおそらく失敗します)。実際、BOSE 社の方へのインタビュー記事を読むと、店舗向け商品で重要なことは「お店本来のサービスの邪魔をしない、目立ちすぎない」「お店の空間が音に包まれている感覚を大事にしたい」といった風なことが書かれていたりします。
121 は BOSE 社の原点とも言える 11.5cm フルレンジユニットをオーディオ向けに仕立て上げた製品で、他の BOSE 社製品と比べると BOSE ならではの味付けは少ないように感じます。ですがオーディオ向けのスピーカー市場は強敵揃いの激戦区で、私も後述の Tangent EVO E4 を使い始めてからというもの 121 の出番がなくなってしまいました。とはいえ、オーディオ用に初めて買ったスピーカーということもあって、なんとか復活させたいという思いはありました。
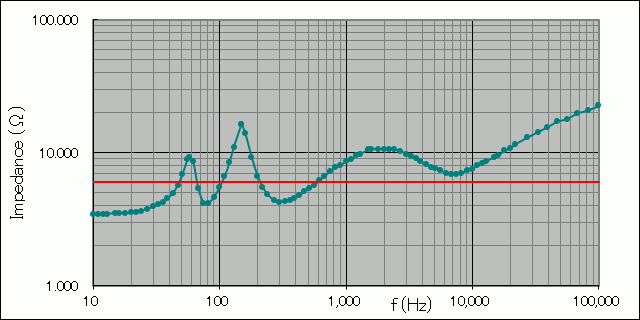
BOSE 121 のインピーダンスを測定してみると、スピーカーユニットの共振周波数 (f0) は約 150Hz で、バスレフポートの共振周波数は約 60Hz くらいにありました。他には 2kHz 付近を頂点とするなだらかなピークがありますが、これはスピーカーユニットと直列に実装されているイコライザー回路によるものと考えられ、インピーダンスが上昇するほどスピーカーの音圧が低下することになるはずです。つまり、中域の音圧を凹にすることで低域・高域のレスポンスが不足しがちなフルレンジユニットの弱点をカバーする意図が読み取れます。
スピーカー背面にある入力端子のパネルを取り外すと、その内側にイコライザ回路の基板が載せられていました。BOSE のイコライザー回路には電球 (!) が実装されていることで有名らしいのですが、121 もご多分に漏れずそこには電球のお姿がありました。電球と並列して何かの部品(イコライザー基板の写真の奥に写っている部品)が接続されていて、基板には "RXE080" と記されていましたがおそらく PTC サーミスタではないかと思います。それと直列に繋がれていたのは LCR 並列回路で、抵抗は 10Ω、コンデンサは 4.7uF、スピーカーインピーダンスのピークが 2kHz であることから、推定されるコイルのインダクタンスは 1.5mH です。フルレンジユニットそのもののインピーダンスは 1.5Ω 程度と低いためユニット単体で使うことはできず、イコライザ回路を使う前提で製品設計がなされていることから、イコライザ回路には手を加えないことにします。


ところで、測定をしている途中で 121 の問題点を見つけました。それはバスレフのダクトが音圧によって振動してしまうことで、音量を大きくしてダクトの出口付近に触れるとはっきり分かります。測定時には 70Hz 付近の音に不自然さを感じたり、ポートの共振周波数よりも低い 50Hz 以下でもスピーカーから音が出すぎているのが気になっていたのですが、おそらくダクトの振動による影響ではないかと思います。そこで、バスレフのダクトを撤去してポートの開口部をホームセンターで買ってきた板切れで塞ぐことにしました。その条件でインピーダンスを測定し直したのが下図のグラフです。

バスレフポートを塞ぐ改造したところ、f0 は実測で 136Hz に下がりました。低音の出方も密閉型スピーカーと同じようになりました……が、聞き比べてみたところ低域のレスポンスは 121 よりもサイズが小さい tangent EVO E4 には負けています(というか、むしろ tangent EVO E4 が優秀すぎるのですが)。それでも出てくる音に荒さを感じたので、ダクトが入っていた関係で吸音材が貼られていなかったスピーカー内部の側面に、これまたホームセンターで買ってきた水槽用のろ過フィルターを1枚突っ込んでみたところ、これがなかなかいい塩梅になりました。ボーカルの存在感が増し定位感も改善されたので、なんとか人前に出せるレベルにはなった感じがします。
……さらにエージングを進めたところ、表現力も改善され侮れないフルレンジスピーカーに化けました。やるじゃないか。


| 方式 | 2Way スピーカー・密閉型 |
| ユニット | 25mm ドーム型ツィーター / 100mm コーン型ウーファー |
| インピーダンス | 4-8Ω |
| 防磁設計 | 〇 |
| 最大出力 | 100W |
| 入力感度 | 87dB |
| 周波数特性 | 70Hz~20,000kHz (±3dB) |
| サイズ | 125(W) x 190(H) x 160(D) mm |
| 重量 | 2.5kg |
ぺるけさんのサイトのページで知って購入したスピーカーで、同じような経緯で購入された方も多いのではないかと思います。正面から見た大きさは新書本よりも若干大きいくらいで、デスクトップに置いても邪魔にならない大きさですが、その割に低音がしっかり出ます。音源によってはもうちょっとボーカルが前に出てきてほしいなぁと感じる場合もありますが、出てくる音のバランスが非常によいので部屋用でも十分に使えます。

tangent EVO E4 の共振周波数 (f0) は実測 108Hz で、このサイズのスピーカーとしては相当に低い値になっています。共振周波数のピークを除けばインピーダンスはおおむね 4~5Ω といったところなので、8Ω端子よりは4Ω端子に繋いだ方がよさそうに思えますが、1kHz のインピーダンスは実測で 7.9Ω あったのでちょっと迷います。
残念ながら tangent EVO は次期モデルの E5 で密閉型からバスレフ型に変更されてしまいましたので、おそらく E5 では E4 と同じような音は出ないと思います(E5 のバスレフポートを詰めたらどうなるか、という可能性はありますが)。E4 の完成度が高かっただけに、なんだか勿体無いなぁという思いがします。ふと tangent EVO E4 の代替候補となりそうなスピーカーを探したりもしますが、なかなか見つからないのが現状といったところです。
| 方式 | 2Way スピーカー・密閉型 |
| ユニット | 19mm ドーム型ツィーター / 110mm コーン型ウーファー |
| インピーダンス | 6Ω |
| 防磁設計 | - |
| 許容入力 | 50W |
| 入力感度 | 83.5dB (1W, 1m) |
| 周波数特性 | 75Hz~20,000kHz (±3dB) |
| サイズ | 190(W) x 306(H) x 184(D) mm |
| 重量 | 6.1kg |
これも同じくぺるけさんのサイトのページで知ったものです。ネットでレビュアーの見解を集めてみますと、とりわけ室内楽との相性が良いらしく、そのあたりもぺるけさんが推していた背景にあるのでしょう。評価の高いスピーカーですが、購入する上で最大のハードルはそのお値段。2020年時点で2台ペアの定価は 340,000円(税抜) でした。アベノミクスによる円安の影響もありますが、前モデルの P3ES と比べると実に2倍近い値上がりです。さらに、P3ESR の後継モデルである P3ESRXD のお値段は 480,000円(税抜) になりました……嗚呼……
そうした事情もあって Harbeth 様の敷居は非常に高く、私も梅田にある某超大型家電量販店3Fにあるスピーカーコーナーの一角に鎮座するその御姿を遠巻きに眺めるだけだったのですが、ある金曜日の仕事帰りに(いつもは寄り道なんかしないのに)お店のスピーカーコーナーにふと足を延ばすと、次期モデルとの入れ替えのためか P3ESR 様が展示処分品として3割引き以上の特価で売りに出されておりました。
……えぇ、この千載一遇のチャンスを私が見逃す筈はございません。次の日、朝一番で来店するなり指名買いしましたとさ。

P3ESR のインピーダンスを測定したところ、中高域に特徴的なうねりのあるグラフになりました。なんだか Rogers LS3/5A のインピーダンスに似ているような、似ていないような……もっとも、P3ESR は LS3/5A の系譜を受け継ぐスピーカーの1つなので、傾向としてそういうところはあるのかもしれません。本体の大きさに余裕があるせいか、共振周波数 (f0) は 78Hz と Tangent EVO E4 よりもさらに低めです。P3ESR の公称インピーダンスは 6Ω ですが、グラフを見る限りアンプの 8Ω 端子の方に繋ぐのが正解のように思います。
そして肝心の音ですが、やはり評判を裏切らない出来です。定位はビシッと決まりますし、ボーカルの存在感、ピアノをはじめとした楽器の表現力、低域の空気感、どれをとっても不足を感じることはなく、音の豊かさではさすがの Tangent EVO E4 も P3ESR には及びません。課題はいかにして安く入手するかということになりますが、オーディオ業界のお約束として日本国内ではお値段が高めに設定されているので、英国国内の通販サイトから forward2me などの転送業者を経由して購入するのが経済合理性のある買い方です(VAT を免税にする方法については各自調べてみてください)。
| 方式 | 2Way スピーカー・密閉型 |
| ユニット | 20mm ドーム型ツィーター / 100mm コーン型ウーファー |
| インピーダンス | 6Ω |
| 防磁設計 | × |
| 推奨アンプ出力 | 30 ~ 120W |
| 入力感度 | 84dB (2.83V, 1m) |
| 周波数特性 | 95Hz~25,000kHz (±3dB) |
| サイズ | 113(W) x 196(H) x 96(D) mm |
| 重量 | 1.5kg |
製作したアンプのデモンストレーション用に持ち運びしやすいスピーカーも1組あったらいいかなと思って、小型の密閉型スピーカーを探してみると数は少ないもののいくつかの機種が検索にヒットします。そのうち私の目についたのは Monitor Audio の Radius 45、DALI の FAZON MIKRO、高井工芸の HC-TX102 といったあたりです。そういえばと思って例のページを見てみると、Monitor Audio R45HD の名前がありました(考えることは一緒かぁ……)。
その中で FAZON MIKRO を選んだのは、スピーカーの体積とウーファーの口径が他候補のスピーカーよりも大きいから低音の出方も幾分かマシだろう……という安直な予想からです。で、実際に買って聞いてみた感想ですが、大方のレビュー通り低音は出ません (^^;

FAZON MIKRO の共振周波数 (f0) は実測 140Hz で、まぁこんなものだと思います。それよりも、800Hz ~ 15kHz にかけての広い帯域でインピーダンスが全体的に高くなっているのが目を引きます。出てくる音は中高域寄りで、このトーンキャラクターを良しとするかどうかは個人の好みが出そうな感じです。もっとも、部屋置きのメインとして使うには低域の薄さゆえに迫力不足で、サテライトスピーカーもしくはデスクトップ用として使うのが妥当なところでしょう。
| 方式 | 2Way スピーカー・密閉型 |
| ユニット | 20mm ドーム型ツィーター / 75mm コーン型ウーファー |
| インピーダンス | 8Ω |
| 防磁設計 | - |
| 推奨アンプ出力 | 15 ~ 50W |
| 入力感度 | 87dB (1W, 1m) |
| 周波数特性 | 120Hz~20,000kHz (±3dB) |
| サイズ | 100(W) x 100(H) x 100(D) mm |
| 重量 | 1.0kg |
お出かけ用スピーカーのもう一つの候補として考えていたものです。R45HD の後継モデルにあたりますが、スペックを見る限りではほぼ同等品と考えてよいと思います。実売価格は 42,000円(税抜) 程度ですが終息傾向にあるモデルらしく、中でも私がほしかった白色モデルは新品での入手が困難なようです……
が、Google 殿に頑張って探してもらったところ、なんと amazon.co.uk に白色モデルの新品が £50 というありえない価格で出品されているではありませんか。英国国内のみ発送可能な業者さんからの出品だったので forward2me を経由して個人輸入いたしました。あーっ、安かった。
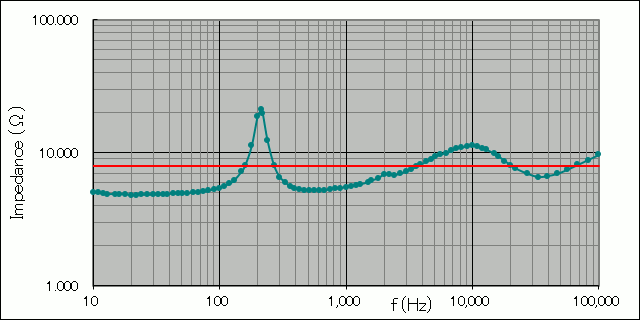
インピーダンスを測定したところ、低中域では共振周波数のピークを除いて 5Ω 程度の値になりました。つまり、Radius 45 は公称インピーダンスである 8Ω ではなく、4Ω あるいは 6Ω の端子に繋ぐのが正解となります。共振周波数 (f0) は実測 214Hz でした。スピーカーユニットの大きさが 75mm しかないので、割り切った使い方が必要です。
ただ、実際に試聴してみた限りでは Radius 45 よりもサイズが大きい FAZON MIKRO に比べて劣っているようには感じられませんでした。むしろ、Radius 45 の方がボーカルがより前に出てくる傾向があります。小さいスピーカーなので低域は全く期待できませんが、中域の厚みは思った以上にあるような感じです。お出かけ用用途としてはサイズ・重量ともに小さい Radius 45 の方がよさそうな気がしますが、まだ聞き込んでいる時間も短いので継続評価ということにします。